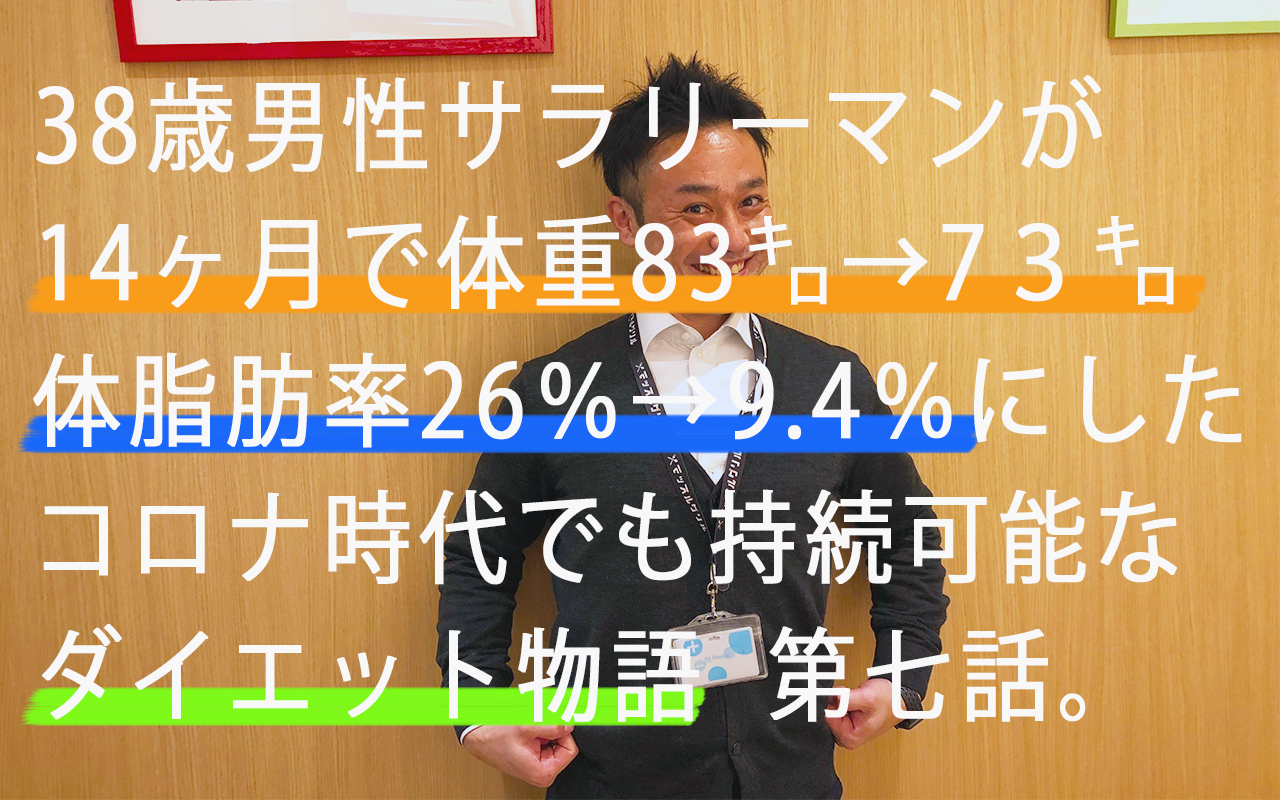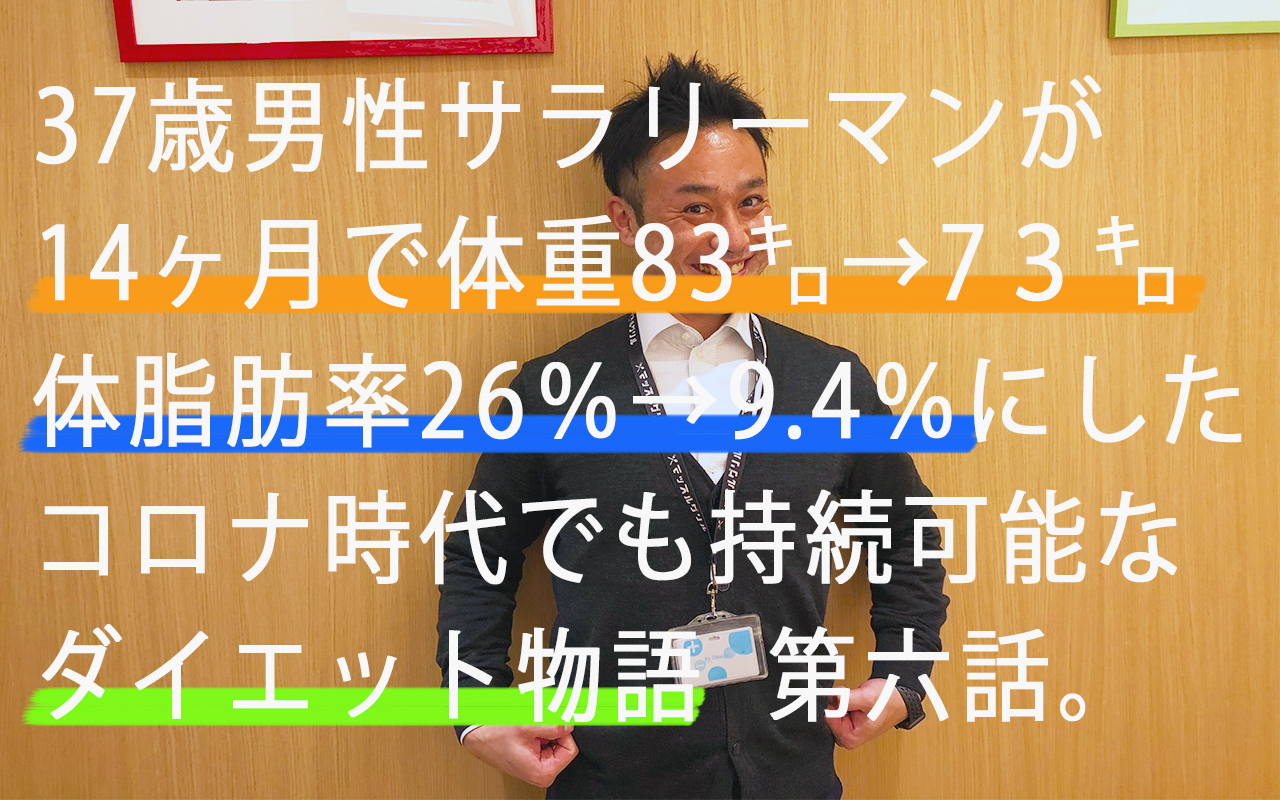はじめまして。わたしの本棚 ライターの環と申します。「SDGs×読書」をテーマとした書評として、今回私がご紹介したいのは「島はぼくらと」という小説です。

あらすじ
この小説は、瀬戸内海に浮かぶ人口が3,000人ほどの小さな架空の島、冴島が舞台です。
次第に子どもから大人へと変化していく主人公たちが抱く、故郷の島への思いがぎゅっと詰まった青春小説ですが、日本の過疎地域の現状や地域おこしについてのエッセンスも込められており、故郷の未来について考えるきっかけもになり得る1冊です。
主人公は4人の高校生たち。母と祖母の女三代で島に暮らす朱里、網元の一人娘である衣花、父のロハス計画で移住してきた源樹、胸に熱い思いを秘めている新。彼ら4人は、この島唯一の同級生で、島には高校がないため本土へ渡るフェリーで通学しています。
フェリーの出航時間は決まっているので、部活にも思うように参加ができず、登下校もいつも一緒でした。一緒に成長してきた彼らですが、高校卒業と同時に島を出ていく者、進学する者とばらばらになってしまうことになります。本書ではそんな幼い頃には予想もしなかった未来が近づく4人の夏の姿が綴られています。

コミュニティーデザイナーという仕事
この小説の作者は辻村深月さん。これまでも地域の閉塞感や世代間の軋轢を感じさせるような小説を、複数執筆されていますが、この「島はぼくらと」は地域のあり方を明るく、肯定するようなお話です。
舞台となる冴島には高校がないため、島で育った子どもたちはみんな進学や就職のため、島を出ていきます。出ていく人がいる一方で冴島は、地域の生き残りのため、IターンやUターンで島に入る人を積極的に受け入れいれています。なぜなら、よそ者を排除するステレオタイプが蔓延った地域のままでは、人口は減るばかりで、活力も縮小してしまうと考えているからです。
もちろん、外側からやって来た人だけでは島おこしは立ち行かず、元からいる人たちと一緒に進めていくことが重要です。そこで、外と内の橋渡しをする役割として、登場するのが「コミュニティーデザイナー」という職業です。主人公のひとりである朱里の母も、島の村長がコミュニティーデザイナー」と連携してつくった会社で働いています。
「コミュニティーデザイナー」は内側か外側か、男か女か、大人か子どもか、といった多様な立場の島民の心を繋ぎ、地域を元気にしていくキーパーソンとして小説の中で描かれています。
この小説は、実際のコミュニティーデザイナーである、西上ありささん(studio-Lメンバー)の話を聞いたことがきっかけで、執筆されたそうです。私も実際のコミュニティーデザイナーは、どうやって地域と関わっているのだろう?と興味を持ち、調べてみたところ studio-L代表・山崎亮さんのインタビューを見つけました。そしてこのインタビューの内容が大変参考になりました。
故郷がなくなってしまう?
少し古い報告になりますが、日本創成会議で発表された報告書(日本創成会議・人口減少問題検討分科会「ストップ少子化・地方元気戦略」平成26年5月8日付)では、2040年までの人口予測に基づくと、全国の800以上の市区町村が消滅可能性都市、というネーミングで消えてしまうかもしれない地域として言及されています。少しショッキングな予測ということで、発表当時は大きな波紋を呼びました。
地域活性化の成功法則として、
- 地域の良さを外から見て客観的に知っている「よそもの」
- 変化を恐れない「わかもの」「ばかもの」が必要だ
という考え方があります。
これまで、この考え方をもとにした成功事例はもちろんありますが、それは今この日本には必ずしも当てはまらないのではないか、と私はこの本を読んだ時に、ふと思いました。
若者は、「島はぼくらと」の主人公たちのように、進学・就職でその地域を出てしまうことが圧倒的に多いのではないでしょうか。「わかもの」が不在のなか、いかに地域おこしの担い手をバトンリレーしていくか、という意味でもコミュニティーデザイナーという仕事は、きっと地域づくりに大切な存在なのだと思います。

結びにかえて
SDGsは「誰一人として取り残さない方法」で、課題の解決を目指しています。行政、住民、事業者、農家、NPOといった様々な立場や組織を越えて、持続可能な地域の未来を実現する地域おこしはまさしくこの「誰一人として取り残さない方法」に沿って活動することが求められています。
私たちの故郷、住む町がどういう未来を迎えてほしいか、ということを考えることから、地域おこしは始まるのかもしれません。